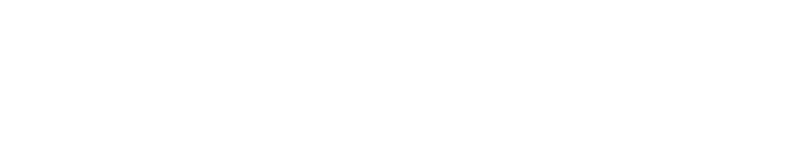5.海上の路Ⅱ六百年の歴史をひも解く



エピソード3 海の路と大寧寺文明史学者川勝平太氏が、かって名著『文明の海洋史観』の中で、日本のDNPがほぼカナダ一国の経済規模の四倍であることに着目し、この国を四つに分割して地政学的な評論を加えた。北海道と東北地方を中心にした「森の国」、 関東一帯をひとまとめにした「野の国」、中部日本を「山の国」、そして西日本を「海の国」と呼ぶ。まことに西南日本は海の国である。海岸線の総延長は図抜けており、津々浦々を結ぶ海の路は複雑に発達してきた。アジアの海に向かって立地し、古来、直近の朝鮮半島や中国大陸の沿海部と濃密な交流を重ねてきた。 この地域は、移民、亡命、交易、略奪、外交、戦争、文化交流、なんでもござれの国際関係史を編み上げており、アジアの海における海上権marine sovereigntyの動向に深く関与した。 ところで、下関市豊北町に肥中と呼ばれる今は人目をひかないありふれた漁港がある。 この港は、じつは中世後期、九州や朝鮮半島を対象とする交易、外交の拠点として大内氏が政策的に整備した要港だった。 この浦に大内の対鮮貿易センターである「御船蔵」が設営され、ここを起点に、滝部―田耕―西市(豊田町)―殿敷 ―大嶺―河原―岩永―綾木―長田とたどり山口の道場門前阿部橋付近に至る16里(約60キロ)の内陸横断道路が整備されていた。この路は「肥中街道」と呼ばれて、 大内時代に整備活用された道路網の中でも特に重要な意味を持つ陸路だった。肥中街道は、アジアの海に進出を図る大内氏の対外政策を象徴しており、その向こうにつながる海上の路と密接に連結されていたのである。 肥中浦に陸揚げされた輸入品は御船蔵に収納され、肥中街道をはこばれて西の都山口に届いた。では、海の交易路はどのように敷設されていたのか。 大内氏の対鮮交易の基地として整備された肥中浦は、李氏朝鮮側の資料に赤間関(下関港)とならぶ長門地域の重要な港として 「長州寶重関」の名前で記載されている。 寶重浦の項には「筑前博多を指す」と注記されたものがあるので、あるいはこの時代、半島東南部の港を出た朝鮮の船は、先ず最短の肥中浦に寄航し、ここから目的地の博多へ向かう航路があったのかもしれない。 肥中港を扼す位置にご存知の角島がある。響灘から 周防灘に至る内海航路、大津北浦の海から東へ向かう日本海ルート、そして九州沿岸、朝鮮半島、中国大陸方面へと伸びていく玄界灘や対馬海峡東水道の船路を結節する大津の海きっての要衝だ。 この角島が、大内時代大寧寺の所領に組み入れられていたことを前稿で触れたが、 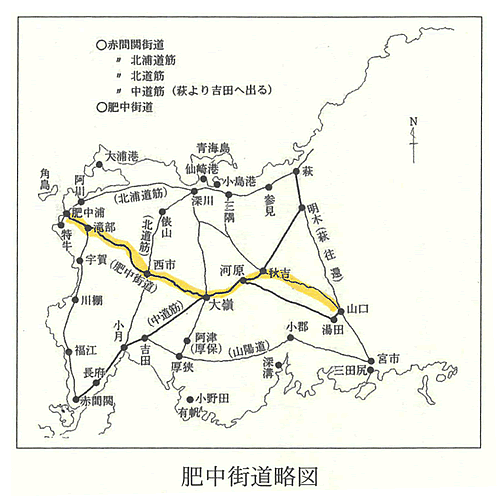 毛利時代の初期になると、
肥中浦や角島などの要地を管轄する阿川毛利家の菩提寺として阿川の浦に大寧寺の末寺海翁寺が設置された。 毛利時代の初期になると、
肥中浦や角島などの要地を管轄する阿川毛利家の菩提寺として阿川の浦に大寧寺の末寺海翁寺が設置された。この角島・肥中地域を基点として東アジアの海に至るスケールの大きな海の回廊を整備していく事業に、大内一族(鷲ノ頭氏をふくむ。)が、大寧寺の本寺―末寺システムを運用した可能性はかなり高い。西欧社会が「大航海時代」として 世界の海に進出した1450年頃から1640頃までを西洋史では「長い16世紀」と呼んでいるが、ちょうどこの「長い16世紀」の同時代に、奇しくも大内氏はアジアの海を志向する「大内ビジョン」を施策し、毛利氏がそれを継承しようとしていたと推定される。 ① 小野田有帆浦の岩崎寺は江戸時代初期に大寧寺末寺に組み入れられたが、その前歴は長く、早くから大内氏の庇護を受けてきた。 ② 有帆浦の対岸、周防灘沿いの要港である豊前広津の広運寺は、1500年代の初期に設置。 同じく、豊前中津城の寿福寺は、千四百年代の末までに大寧寺末寺に組み入れられている。 寿福寺の立地する周辺は古来「瀬戸崎鷹匠町」と呼ばれたが、大内氏が李朝から輸入したもっともステータスの高い貴重な輸入品が朝鮮鷹と鷹匠だったことを想起させる。 ③ さて、角島を左折して玄界灘に入る最初の要港は、遠賀川河口の芦屋(あしや)津(現在の岡垣町)である。芦屋の古刹龍昌寺(末寺六ヶ寺)は、中津の寿福寺と同時期1400年代後半に大寧寺末寺として設立された。 芦屋津は、大津の瀬戸崎(仙崎)と同様、往古より鋳物・鉄産業の中心地だった。 茶道で珍重される芦屋釜や寺院の芦屋鐘は、朝鮮のモデルによってここで生産された。現在大寧寺に残っている梵鐘も芦屋製である。 ④ 博多の箱崎神社は大内氏が整備し、社家は、宗像大社と同じく大内家の有力武将だった。箱崎神社資料に、毎年夏の決まった時期に大寧寺の僧侶団が来訪し博多湾に向かう社殿で「大般若(だいはんにゃ)」の儀式を修した記載が残っている。 海の路の安全を祈願する行事だった。 ⑤ 壱岐の島は、南部の郷ノ浦港に華光寺(末寺六五ヶ寺)、 また北部の芦辺浦に竜蔵寺(末寺24ヶ寺)が、共に1550年代に大寧寺末として造立され、 島内全域の港にこの両寺の 又末寺が展開している。 ⑥ 対馬の厳原港近郊の国分寺 (領主宗氏の菩提寺)が大寧寺末寺に組み入れられたのは、 芦屋津の龍昌寺と同時期の1450年代。大寧寺の四世大円寺竹居正猷(ちっきょしょうゆう)や 鷲ノ頭弘忠が活躍した応永、嘉吉、文安年間にあたる。 大寧寺の本末関係を活用したもっとも初期の外交・商業ルートではなかったか。江戸時代の僧録制度によって寺院数が増えたとはいえ、 島内の港や浦々に130ヶ寺もの大寧寺孫末が展開している有様は、現代人のわれわれの想像を絶する。 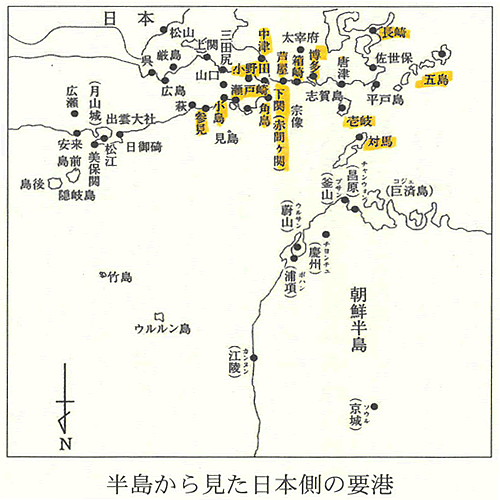 ⑦ 五島列島福江島の福江浦には、1500年代までに、大寧寺末大円寺 (領主、五嶋氏の菩提寺。末寺24ヶ寺)が設営されている。大円寺系の孫末も五島の島々一帯にびっしりと展開している。 ⑧ 同じく五島列島の北端の島宇久島(倭寇(の有名な出撃基地)には、1550年代に 大寧寺末寺東光寺(末寺7ヶ寺)が造立された。 ⑨ 長崎湾沿いの深堀港に、早くも1450年代に大寧寺末寺菩提寺(ぼだいじ)(末寺4ヶ寺)が設置された。 ⑩ 同じく、大村湾の要港諫早港に、竜造寺氏の菩提寺として 1400年代末までに天佑寺が設営されている。この古刹も大寧寺の末寺であり大内氏の支配下にあった。天佑寺の数多い末寺(10ヶ寺)は一帯の津々浦々に効果的に配置されている。(「海の路」おわり) (註)甲寺の住職が乙寺の開山となっている場合、甲寺を乙寺の本寺と呼び、 乙寺を甲寺の末寺あるいは末山、と呼ぶ。 |